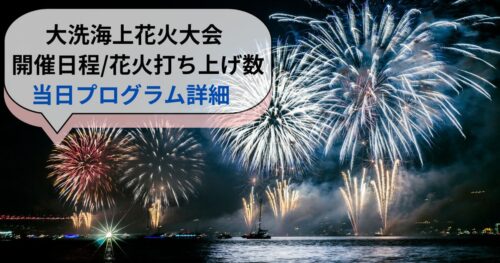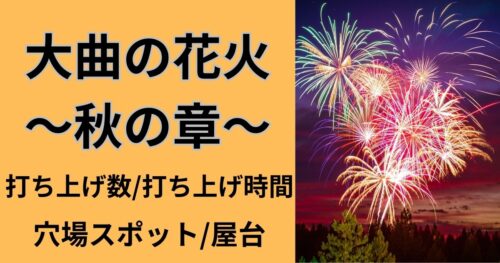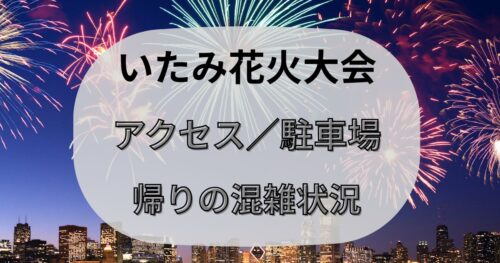夏の和歌山を代表する伝統行事田辺祭り(たなべまつり)をご存知でしょうか?
紀州三大祭のひとつとして知られ、毎年7月24日・25日に田辺市で開催される闘鶏神社の例大祭です。
450年を超える歴史を持ち、町中を豪華なおかさ(笠鉾)が練り歩く様子は、まさに壮観。この記事では、田辺祭りの由来や歴史、見どころ、そしておかさとは何かについて、分かりやすく解説します。

田辺祭りは歴史と迫力が魅力!
おかさ巡行と伝統神事が見どころです
起源は16世紀!田辺祭りの歴史と由来をひも解く
田辺祭りの起源は、16世紀中頃までさかのぼります。1605年(慶長10年)には、すでに祭礼で車が使われた記録が残っており、460年以上続く伝統行事として和歌山県無形民俗文化財にも指定されています。
その後、1607年に**流鏑馬(やぶさめ)**が登場し、1633年には能の奉納、1672年には笠鉾に車が付けられるなど、時代とともに進化してきました。
商人町の文化が神事に融合し、現在のような町を挙げての祭りへと発展したのです。



起源はなんと戦国時代!
商人文化と神社神事の融合が田辺祭りのルーツです
見どころ満載!2日間にわたる神事と幻想的な光景
田辺祭りでは、2日間にわたり多彩な神事や催しが行われます。中でも有名なのが、以下のような伝統行事です。
主な見どころ一覧
| 見どころ | 内容 |
|---|---|
| お旅所勤め | 各町の笠鉾が神輿とともに漁港へ進み、神官が潮かけの儀式を行う |
| 住矢の走り | 笠鉾の先導役「住矢」が町を駆け抜け、厄除けを祈願 |
| 会津橋曳き揃え | 夜、橋の上に笠鉾が勢揃いし、提灯が水面に映る幻想的な光景 |
| 宮入り | 笠鉾が闘鶏神社の鳥居から境内へ続々と入場し、祭りのクライマックスに |
| 流鏑馬 | 稚児が馬に乗って矢を放つ魔除け神事(25日夜) |
特に会津橋曳き揃えは写真映え抜群!夕暮れ時に訪れるのがおすすめです。



潮かけや流鏑馬など神事が豊富!
夜の曳き揃えはインスタ映え間違いなし
おかさとは?田辺祭りの主役、笠鉾の魅力とは
田辺祭りの象徴ともいえるのがおかさ(笠鉾)。これは、山車の一種で、京都・祇園祭の山鉾の影響を受けた豪華な曳山です。
旧城下町の8つの商人町から、それぞれ1基ずつ出される笠鉾は、高さ・装飾・構造すべてが異なります。笠の中では小学生たちが笛や太鼓でお囃子を奏で、町ごとの伝統が息づいています。
しかも、装飾された人形や飾りは毎年丁寧にメンテナンスされ、まさに“動く工芸品”。曳き回される姿は圧巻です。



おかさは8基すべて違う!
中で子どもたちが生演奏する町の宝です
田辺祭りってどんな雰囲気?地域ぐるみで盛り上がる夏の風物詩
田辺祭りは、単なる見物する祭りではなく、地域の人々が一丸となって作り上げる夏の風物詩。町内の方々が白装束や浴衣姿で参加し、町全体が祭り一色になります。
また、夜になると屋台も並び、グルメや遊びも満喫可能。伝統と賑わいが共存する“生きた文化財”のようなお祭りです。観光客も多く、年々注目が集まっています。



田辺の夏=町中が祭りモード!
伝統文化と現代の楽しさが融合してます
✅ まとめ|田辺祭りは歴史×賑わい×美しさが詰まった夏祭り!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 祭り名 | 田辺祭り(たなべまつり) |
| 開催日 | 毎年7月24日・25日 |
| 開催地 | 和歌山県田辺市・闘鶏神社周辺 |
| 起源 | 16世紀中頃(約460年前) |
| 見どころ | おかさ(笠鉾)巡行、会津橋曳き揃え、住矢の走り、流鏑馬 ほか |
| 特徴 | 神事・町衆文化・子どもたちのお囃子が融合した町全体の祭礼 |



おかさと伝統神事が織りなす2日間!
田辺の夏は、この祭りを見ずして語れません
今年の夏は田辺祭りで特別な思い出を!
田辺祭りは、**歴史・文化・地元の誇りが凝縮された“和歌山の夏の象徴”**です。
2025年も、7月24日(木)・25日(金)の開催が予定されています。



おかさの迫力、夜の幻想的な光景、神事の荘厳さ。どれをとっても一見の価値あり。
ぜひ、夏の予定に「田辺祭り」を組み込んでみてくださいね