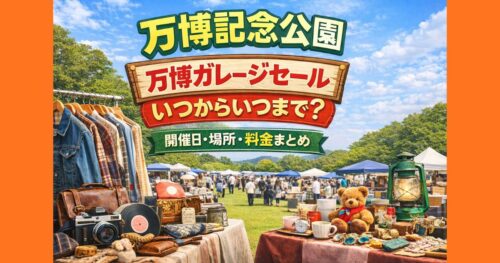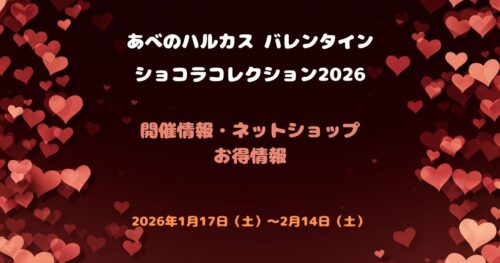京都の夏の終わりを彩る五山送り火(ござんおくりび)。8月16日の夜、京都の山々に火文字が浮かぶこの行事は、観光名所としてだけでなく、亡き人への祈りと感謝を込めた厳かな伝統でもあります。
今回はその読み方や歴史、いつから始まったのか、そしてその魅力について詳しくご紹介していきます。
五山送り火ってなんて読む?通称と正式名称の違い

読み方はきょうと ござん の おくりび。よく耳にする大文字焼きは実は通称です!
京都五山送り火は、**正式な読み方はきょうと ござん の おくりび**です。
五山と書いてごさんではなくござんと読みます。
地元では大文字焼きとも呼ばれることがありますが、これは本来の意味を正確に表しているわけではありません。
送り火は、お盆に戻ってきた精霊を再びあの世へ送り返す、仏教的な意味を持つ宗教的な儀式です。
その意味を尊重するなら、五山送り火と呼ぶのがよりふさわしいのです。
いつから始まった?起源には諸説アリ



はじまりには平安〜江戸までさまざまな説が。現在の形は江戸時代中期からと考えられています!
五山送り火の起源ははっきりとは分かっていません。
いくつかの説が存在しており、たとえば:
- 空海(弘法大師)が始めたという説(平安時代)
- 足利義政が考案した説(室町時代)
- 能筆家の近衛信尹が始めた説(江戸時代)
しかし、これらは伝承の域を出ず、確かな証拠は確認されていません。
文献上で大文字焼きとして登場するのは15世紀以降であり、現在のように五つの山で順次点火される形式が定着したのは江戸時代中期とされています。
つまり五山送り火は、少なくとも300年以上の歴史を持つ由緒ある伝統行事なのです。
送り火の意味と仏教的な背景



精霊を送るための火は、亡き人への祈りを込めた仏教行事。京都では暮らしと信仰が一体化しています。
五山送り火は、お盆の間に帰ってきた**ご先祖の霊(精霊)を再びあの世に送り返すための送り火**です。
この送り火は、日本各地にさまざまな形で存在しますが、京都のものは五つの山に火文字を描くという壮大なスケールで知られています。
それぞれの山の火文字にも意味があり、仏教的な象徴や地域の信仰が表れています:
- 大文字…大日如来や大徳を象徴
- 妙・法…仏教の教え「妙法蓮華経」から
- 舟形…霊をあの世へ運ぶ舟
- 左大文字…大文字と対をなす
- 鳥居形…神域へ導く入口
また、かつては「い」「一」「蛇」などの送り火があったとも伝えられており、時代とともに形を変えながら今日に至っています。
京都の夜空を照らす幻想と荘厳さ―五山送り火の魅力



祈りを込めて灯される炎の美しさは、ただの観光イベントではなく、静かな感動を与えてくれます。
五山送り火の最大の魅力は、夏の夜空に浮かぶ巨大な炎の文字と、それを見守る人々の静けさです。
賑やかな祭りとは違い、送り火は静かで荘厳な雰囲気の中で行われます。
火が灯るたびに人々は静かに手を合わせ、亡き人への祈りを捧げます。
また、京都では送り火の**消し炭を魔除けとして持ち帰る風習**があり、この炭を玄関に吊るして家内安全を祈る家庭も少なくありません。
ただ美しいだけでなく、日常生活にも溶け込んだ信仰の象徴として、人々に受け継がれてきた行事なのです。
市民に支えられて今も続く伝統



火を灯す裏では、地域の人々や学生たちが準備に汗を流しています。五山送り火は生きている伝統!
五山送り火は、観光客向けのショーではありません。地元住民や学生ボランティアによる入念な準備によって支えられているのです。
点火される前には、山に登って火床を掃除し、薪を組み上げる作業があります。
さらに、当日の安全確認、消火体制なども整えられ、自然との共生を意識した配慮もなされています。
特に近年は気候変動や山火事リスクへの配慮から、実施判断がより慎重になっており、火を灯すことの重みが一層増しているといえます。
五山送り火は、まさに**人と自然と祈りが交わる生きた文化遺産**なのです。
まとめ:五山送り火は京都が誇る「静かなる祈りの炎」



ただの観光行事ではない、京都の信仰・生活・歴史が息づく一夜。ぜひ現地でその空気を感じてみて!
京都五山送り火は、単なる観光イベントにとどまらず、
数百年にわたる信仰と文化の結晶です。
- 正式名称は京都五山送り火(きょうとござんのおくりび)
- 起源は不明ながら、江戸時代には確立された歴史行事
- 精霊をあの世へ送り返す仏教的意味合いを持つ
- 夜空に浮かぶ炎文字が幻想的で荘厳
- 地元住民の手によって今も丁寧に受け継がれている
もし夏の京都を訪れる機会があれば、観光だけでなく、この祈りの夜に耳と心を澄ませてみてください。
五山に灯る静かな火が、きっとあなたの心にも何かを届けてくれるはずです。